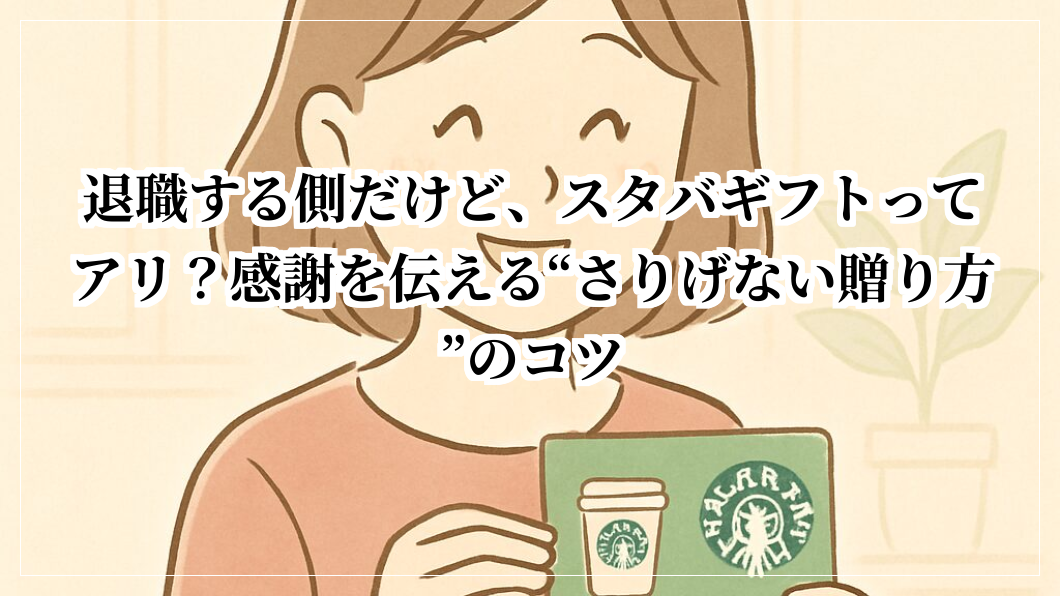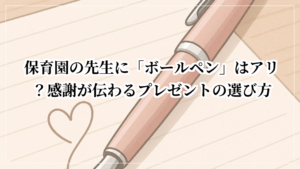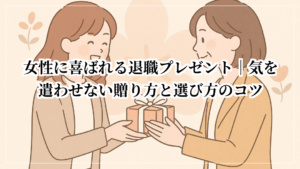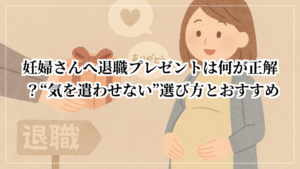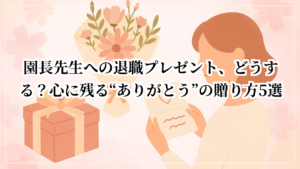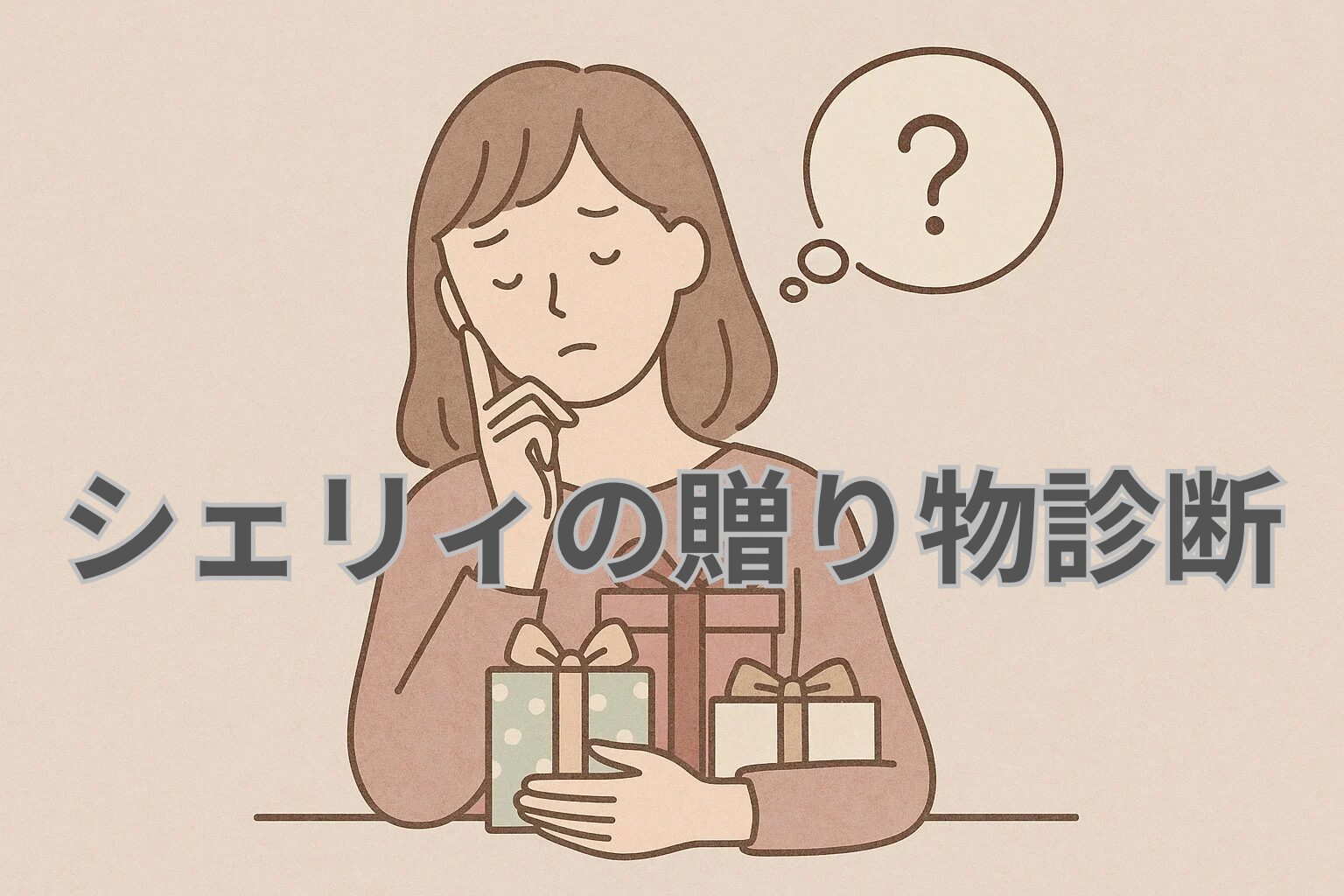読者さん
読者さん退職のタイミングで「お世話になった方にお礼がしたい」と思っても、 “退職する側からプレゼントを贈るのはマナー的にどうなんだろう?”と 立ち止まってしまう人は少なくありません。
特に最近は、気軽に渡せるスタバギフトが候補に挙がりやすい一方で、 「安っぽく見えない?」「非常識だと思われない?」 そんな不安の声があるのも事実です。
でも実は、スタバギフトは “退職時の感謝を、重くならずに伝えたい人”にこそ向いている贈り物。 選び方と渡し方さえ押さえれば、 気を遣わせず、印象よく感謝を伝えることができます。
この記事では、退職する側がプレゼントを贈っても問題ない理由と、 スタバギフトを「さりげなく、感じよく」渡すための考え方を 具体例とあわせて紹介します。
この記事でわかること
- 退職する側からプレゼントを贈っても失礼にならない理由
- 退職ギフトにスタバが選ばれる3つの理由
- 相手に気を遣わせない金額・渡し方・タイミング
- スタバ以外も検討したいときの無難なお礼ギフト
- 退職時のプレゼントに関するよくある疑問



退職する側なのにプレゼントを渡してもいいの?
「退職する側がプレゼントを渡すのは、ちょっと変じゃない?」 そう思って躊躇してしまう方も多いですが、実はマナー的にもまったく問題ありません。 むしろ、これまでお世話になった人へ感謝を伝える行為として、とても自然で好印象なことなんです。
お世話になった人に“ありがとう”を伝えるのは自然なこと
退職は、これまで一緒に働いた人たちへ「ありがとう」を伝える節目でもあります。 立場が“去る側”であっても、「お世話になりました」という気持ちを形にするのは、社会人として丁寧な姿勢。 特に、日頃からサポートしてくれた上司や同僚にとっては、感謝の言葉や心遣いそのものが嬉しいものです。



マナー的にも“問題なし”なケースがほとんど
実際、退職時にお菓子やちょっとしたギフトを渡すのは、多くの職場でよく見られる光景です。 最近では特に、「気軽に受け取れて、相手に負担をかけないお礼ギフト」が主流になっています。
ただし注意したいのは、高価すぎるものや、個人的すぎる贈り物。 お礼のつもりが「お返しを考えなきゃ…」という負担になってしまうと、本来の目的からズレてしまいます。
大切なのは“受け取る側に気を遣わせないこと”
退職時のプレゼントの目的は、あくまで「感謝を伝えること」。 そのためには、価格・内容・渡し方を控えめにするのがポイントです。
このバランスを自然に取りやすいのが、 気軽でおしゃれ、なおかつ実用的なスタバギフト。 次の章では、なぜ退職ギフトとしてスタバが選ばれているのか、その理由を詳しく見ていきます。



なぜ“スタバギフト”がちょうどいいの?
退職時のプレゼントとして人気が高いのが、スターバックスのギフトカード。 「おしゃれで気を遣わせない」「もらって困らない」という声が多く、 ここ数年で“定番のお礼ギフト”としてすっかり定着しています。
では、なぜ数あるギフトの中からスタバが選ばれているのでしょうか? その理由を見ていきましょう。
重すぎず、気軽に受け取ってもらえる
スタバギフトの最大の魅力は、“軽やかさ”と“スマートさ”。 500円〜1,000円前後から選べるため、 相手が「お返しを考えなきゃ」と感じにくい価格帯です。
それでいて、スターバックスというブランドの安心感があるので、 「とりあえず感」や「安っぽさ」は出ません。 感謝を伝えるのに、ちょうどいい距離感のギフトなんです。
気を遣わせたくないなら、500〜1,000円程度のスタバカードがちょうどいい金額です。



“カジュアルだけど気持ちが伝わる”絶妙なバランス
スタバギフトは、相手が使うタイミングを選びません。 仕事の合間に、休日のリラックスタイムに―― 「好きなときに使える一杯」を贈ることができます。
つまりこれは、モノを贈るというより 「ホッとできる時間」を贈るギフト。 退職という少し改まった場面でも、重くなりすぎず、 自然に気持ちを伝えられるのが魅力です。
デザイン・使い勝手・価格のバランスがちょうどいい
スタバカードはデザインの種類が豊富で、 シンプルなものから限定デザインまで選択肢があります。 また、実物のカードだけでなく、電子ギフトもあるため、 対面でもオンラインでも渡しやすいのがポイント。
「誰でも使える」「センスがいい」「負担にならない」―― このバランスが取れているからこそ、 スタバギフトは“失敗しにくい退職ギフト”として選ばれているのです。
次の章では、実際にスタバギフトを渡すときの タイミングや一言メッセージのコツを紹介します。



退職時にスタバギフトを贈るときのコツ
スタバギフトは便利で万能ですが、渡し方やタイミングを少し意識するだけで、 「とりあえず」ではなく“ちゃんと考えてくれた感”が伝わります。 ここでは、退職時にスタバギフトを贈るときに押さえておきたい3つのコツを紹介します。
相手の人数に合わせて“分けやすい形”を選ぶ
部署やチームなど、複数人に渡す場合は、 1人ずつ手渡しできる形を意識するとスマートです。
たとえば、スタバカードを小さな封筒に入れたり、 一言メッセージを添えるだけでも印象は大きく変わります。 「みんなまとめて」ではなく、1人ひとりに向けた気遣いが伝わる工夫です。



メッセージカードを添えると、気持ちがきちんと伝わる
退職ギフトでは、実はギフトそのものより“一言メッセージ”のほうが印象に残ることも少なくありません。
「お世話になりました」「一緒に働けてよかったです」など、 長い文章は不要。 短くても、自分の言葉で書かれた一言があるだけで、 受け取る側の感じ方は大きく変わります。
口頭で伝えるのが少し照れくさいときや、 忙しくてゆっくり話せない場合でも、 カードを添えればきちんと感謝の気持ちが届くのがメリットです。
渡すタイミングは“最終日か前日”がベスト
退職当日は、挨拶や手続きで意外と慌ただしくなりがち。 そのため、最終日またはその前日に、 落ち着いたタイミングを見つけて渡すのがおすすめです。
送別会がある場合は、 「これ、よかったら使ってください」と一言添えて手渡すだけで十分。 大げさにしすぎないことが、相手に気を遣わせないコツです。
これらのポイントを押さえれば、スタバギフトは 軽すぎず、重すぎない“ちょうどいいお礼”になります。 次の章では、スタバ以外でも使いやすいおすすめギフトを紹介します。



スタバギフト以外でも喜ばれる“お礼ギフト”
スタバギフトは万能ですが、 「職場の雰囲気的にスタバは避けたい」 「もう少し“きちんと感”を出したい」 そんな理由で、別の選択肢を探している方もいるでしょう。
ここでは、退職時のお礼として選びやすく、 なおかつ相手に負担をかけにくい“スタバ以外のギフト”を紹介します。
① お菓子の詰め合わせ(消え物で安心)
退職ギフトとして根強い人気があるのが、 焼き菓子やクッキーなどの詰め合わせ。
消え物なので相手に気を遣わせにくく、 個包装タイプなら部署やチームにも配りやすいのが魅力です。 味はシンプルで万人受けするものを選ぶと、失敗しにくくなります。
中でも、「ちゃんとした印象」を残したい場合に選ばれているのが、 老舗ブランドのお菓子ギフトです。
見た目に上品さがあり、 「お世話になりました」という気持ちをさりげなく、でも丁寧に伝えられます。



② 紅茶・コーヒーギフト(好みを問わず使いやすい)
紅茶やコーヒーのギフトも、 性別や年代を問わず選びやすい定番です。
「お疲れさまでした」「ほっと一息ついてくださいね」 そんな気持ちを自然に込められるのが、飲み物ギフトの良さ。 個包装タイプを選べば、オフィスでも自宅でも使いやすくなります。
③ 個人向けなら“実用的なプチギフト”も選択肢に
特にお世話になった方や、 個人的に渡す場合は、実用的なプチギフトも候補になります。
ハンドクリームなど、 日常的に使えるものを選べば、 重くなりすぎず、気持ちだけをさりげなく伝えられます。 香りは控えめなものを選ぶのがポイントです。
スタバギフトと同じく、 これらのギフトも「軽やかで、でも失礼にならないお礼」として最適。 次の章では、退職時のプレゼントに関する よくある疑問やマナーについてまとめて解説します。



よくあるQ&A|退職時のギフトマナーと注意点
Q1. 退職する側がプレゼントするのは非常識?
A. まったく非常識ではありません。 むしろ、お世話になった人へ感謝を伝える丁寧な行動として、好印象に受け取られることがほとんどです。
注意したいのは、 高価すぎるもの・個人的すぎるものを選ばないこと。 「お世話になりました」という気持ちを、 軽やかに伝えられるギフトを意識しましょう。
Q2. スタバカードの金額はいくらが適切?
A. 一般的には500円〜1,000円程度が目安です。 このくらいの金額であれば、 相手に「お返しを考えなきゃ」と思わせにくく、 “気が利いているお礼”として受け取ってもらえます。
デザインもシンプルなものを選べば、 上司・同僚どちらにも渡しやすくなります。



Q3. 個人的に渡してもいい?
A. 個人的に渡しても問題ありませんが、 職場全体への配慮は忘れないようにしましょう。
特に上司や異性に渡す場合は、 「お世話になりました」と明るく一言添えることで、 誤解を招きにくくなります。 高額なギフトや、特別感が出すぎるものは避けるのが無難です。
Q4. 男性上司にもスタバギフトを渡していい?
A. はい、問題ありません。 スタバギフトは性別を問わず使えるユニセックスなギフトです。
コーヒーが苦手な方でも、 紅茶やスイーツに使えるため安心。 ラッピングやメッセージをシンプルにすれば、 ビジネスシーンにも自然になじみます。
Q5. お礼のメッセージはどう書けばいい?
A. 長文を書く必要はありません。 短くても、自分の言葉で書くことが大切です。
たとえば、 「短い間でしたがお世話になりました」 「これからもご活躍をお祈りしています」 といった前向きな一言で十分。
直接伝えにくい場合は、 メッセージカードを添えるだけでも、 気持ちがきちんと伝わります。



まとめ|“ありがとう”を軽やかに伝えるのが大人のマナー
退職のタイミングでスタバギフトを贈るのは、決して非常識ではありません。 むしろ、「お世話になった人へ感謝を伝えたい」という、 丁寧で好印象な気持ちの表れです。
重くなりすぎず、それでいて気持ちはきちんと伝わる。 スタバギフトが退職シーンで選ばれているのは、 このちょうどいいバランスにあります。
- 退職する側がプレゼントを渡すのはマナー的にも問題なし
- スタバギフトは軽やかでセンスのあるお礼として使いやすい
- 500〜1,000円程度が相手に気を遣わせにくい価格帯
- 一言メッセージを添えるだけで、印象はぐっと良くなる
感謝を伝えるときに大切なのは、 「何を贈るか」よりも「どう気持ちを伝えるか」。 あなたの「ありがとう」という想いがあれば、 それだけで十分に素敵な贈り物になります。
もし「何を選べばいいか迷っている」なら、 この記事で紹介した中から、無理なく用意できるものを選べば大丈夫です。
迷ったらこれ:気軽に渡せて失敗しにくい定番ギフト
気持ちをしっかり伝えたいなら:一言添えるだけで印象アップ
スタバ以外を選びたい場合:きちんと感のある安心ギフト
感謝の伝え方をもっと知りたい方は、 気を遣わせない退職プレゼント や プレゼントの渡し方マナー の記事も参考にしてみてください。